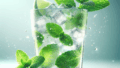これまでのビルドログで、我々は「究極のモヒート」という明確なゴールから逆算し、システムを論理的に設計し(Vol.1)、物理的な環境を構築しました(Vol.2)。理論は完璧です。ハードウェアは実装されました。しかし、どんなに優れた設計も、優れた運用(オペレーション)が伴わなければ、その真価を発揮することはできません。本当の戦いは、ここから始まります。
このビルドログVol.3では、構築したシステムを実際に稼働させ、日々の水やりという最も基本的なタスクを、いかにデータに基づいて最適化していくか、そのPDCAサイクルの全記録を、思考プロセスと共に詳細に公開します。これは、もはや園芸の記録ではありません。複雑な生物システムに対する、システムエンジニアリングの実践記録です。
運用の基本哲学:感覚からデータへ
あなたのディープリサーチで明らかになった通り、初心者が失敗する最大の原因は「水やり」です。そして、その失敗の根源は「感覚への依存」にあります。「土が乾いた気がする」「昨日あげたから今日はいいだろう」。これらは全て、再現性のない、極めて非論理的な判断基準です。我々は、この不確実性を完全に排除します。
我々の運用基本方針はただ一つ、「全ての意思決定は、観測されたデータに基づいて行われる」です。感情や習慣、思い込みが介在する余地はありません。我々が信じるのは、センサーが示す客観的な数値だけです。これにより、我々の栽培プロセスは、誰が実行しても同じ結果が得られる、再現可能なものとなります。
システムの心臓部:静電容量式土壌水分センサーの役割
この運用の心臓部となるのが、Vol.2で導入した「静電容量式土壌水分センサー」です。このデバイスは、単に土の湿り気を測るだけのものではありません。それは、我々のシステムの状態をデジタル言語に翻訳してくれる、最も重要な「インターフェース」です。我々はこのデバイスから送られてくる「土壌水分量」「照度」「周辺温度」という3つのパラメータをリアルタイムで監視し、システムの健全性を評価します。
PDCAサイクル Week1:ベースラインの確立と最初のフィードバックループ
ここからは、最初の1週間の、具体的なオペレーションログを公開します。これは、我々のシステムにおける最初の「スプリント」です。
【Plan】計画:最初の1週間の目標
最初のスプリントの目標は、システムの安定稼働を確認し、水やりを実行すべき「しきい値」の仮説を立てるための基礎データを収集することです。具体的には、以下のタスクを設定しました。
- 毎日午前9時に、水分量、照度、温度を定点観測し、司令塔(Googleスプレッドシート)に記録する。
- 水分量が40%を下回ったら、最初の水やりを実行する。
- 水やり前後でのデータ変化を記録し、システム応答を評価する。
【Do】実行:オペレーションログ
Day 1 (月): システム稼働開始
Vol.2で構築したシステムに、主役であるイエルバ・ブエナの苗を正式に植え付け、運用を開始。初期キャリブレーションとして、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与え、30分後の水分量を「100%」と記録。この日の天気は晴れ。最高気温28度。このベースラインが、今後の全ての測定の基準点となります。
Day 2 (火): 最初のデータポイント
午前9時の測定。水分量は85%。前日の晴天で、予想通り水分が蒸発しています。しかし、まだ我々が設定した40%のしきい値には程遠い。水やりは実行せず、監視を継続します。この「何もしない」という意思決定もまた、データに基づいた重要な判断です。
Day 3 (水): 変化の加速
午前9時の測定。水分量は65%。晴天が続き、減少ペースが加速していることがデータから読み取れます。照度センサーも高い数値を示しており、光合成が活発に行われている証拠です。しかし、まだしきい値には達していません。ここでも、我慢の監視を続けます。
Day 4 (木): しきい値到達と最初の介入
午前9時の測定。水分量はついに38%。我々が設定したしきい値「40%」を下回りました。これこそが、システムが我々に「介入せよ」と送ってきた、最初のシグナルです。ここで初めて、水やりを実行します。ルールはただ一つ、「鉢の底から水が流れ出るまで、たっぷりと与える」こと。実行後、30分後の水分量が98%まで回復したことを確認し、記録。システムの応答は正常です。
【Check】評価:最初のデータセットからの洞察
最初の4日間のデータから、いくつかの重要な洞察が得られました。
- 我々のシステム環境(晴天、気温28度前後)では、約3日間で水分量が60%以上減少することが判明しました。
- 水やり一回で、水分量はほぼ100%まで回復し、システムの応答性に問題はないことが確認できました。
- しきい値40%での水やりは、ミントの葉が萎れるなどの物理的な兆候が出る前に行動できる、安全な範囲であることが示唆されました。
【Action】改善:次のスプリントへのアクションプラン
この洞察に基づき、次のスプリント(次週)へのアクションプランを策定します。
- 水やりのしきい値を、引き続き40%で運用し、データの再現性を確認する。
- 天候(曇りや雨の日)が水分量の減少ペースにどう影響するかを測定するため、天気データも併せて記録する。
- 司令塔シートに、水分量の推移を可視化するためのグラフを作成し、より直感的な状況判断を可能にする。
このように、我々は感情や経験則ではなく、観測されたデータと、それに基づく論理的な改善サイクルによって、システムを常に最適化し続けます。
まとめ:我々は栽培しているのではない、システムを運用しているのだ
このビルドログを通して、我々がやっていることが、単なる「植物のお世話」ではないことがお分かりいただけたでしょうか。我々は、インプット(水、光)とアウトプット(植物の成長)を持つ複雑なシステムを、データという名の計器盤を見ながら、常に最適な状態に保つための「オペレーション」を行っているのです。この制御と最適化のプロセスこそ、我々が提供する価値の核心です。
次回予告:Part 4 – 収穫と究極の成果物
システムは安定稼働を開始し、我々のミントは順調に成長しています。次回、いよいよこのプロジェクトの最終ゴールである「収穫」、そして、我々が育て上げた最高のミントを使った「究極のモヒート」の完成へと進みます。ご期待ください。